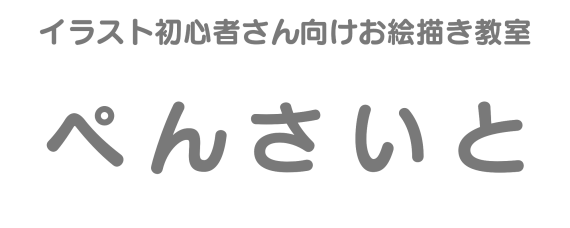この記事を読むのに必要な時間は約 10 分です。
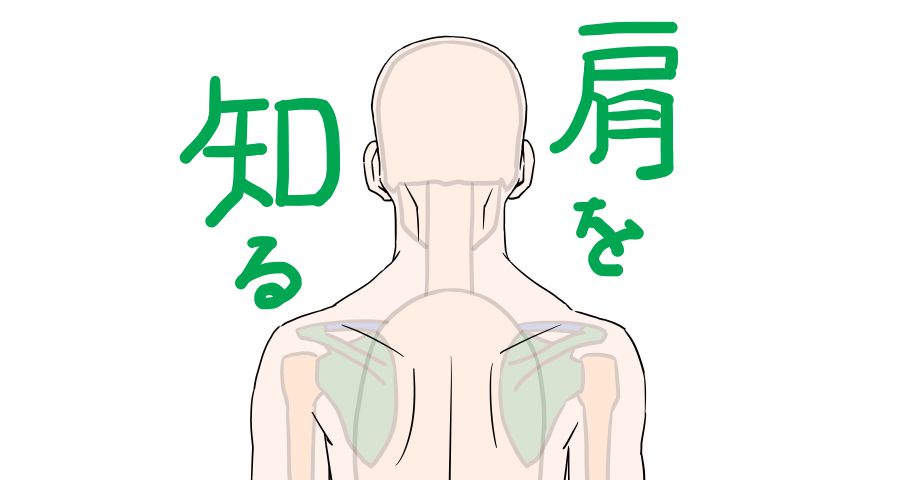
Top画像:肩の構造~後ろ向き
肩回りって具体的にどうなってんのー?
と思うなら、
肩の構造をだいたい知っておくことで、
何かを見ながら描くなどをするときにも
イメージがしやすくなります。
イラストで人物(キャラクター)を
描くときには、肩回りも大事な
イメージ作りのひとつですよね。
肩回りの大きさ・厚み・姿勢などの
描き方ひとつで、
キャラクターの印象は大きく変わります。
そんな「肩」ですが…
人を見て描こうとしても、
「いったい、どうなってるの??」と
感じることも多いはず。
イラストに描けるようになるためには、
まずその中身(構造)を「知ること」が大切。
今回は肩回りの構造を簡単に
見ていくことにしましょう。
肩の骨はどうなっているの?
肩ってけっこう複雑に見えるんですよね。
しかし実際に肩を構成している骨って、
実は2つしかないのですよ。
骨の数は少ないのに、動きは多様で複雑。
肩は多くの靭帯や筋肉が関与しているけれど
ここではすべて割愛!
ややこしいんでね…(^_^;)ゞ
手っ取り早く把握するには、
まず土台となる骨から入っていきます。
てことで、肩の骨を見てみましょう。
【図1-1: 横、前から見た肩の骨】

図1-1:横、前から見た肩の骨
肩を構成している骨は主に2つ。
- 鎖骨(さこつ)
- 肩甲骨(けんこうこつ)
鎖骨は、胸骨と肩甲骨との橋渡し。
胸骨~鎖骨~肩甲骨で繋がる。
【図1-2:後ろから見た肩の骨】
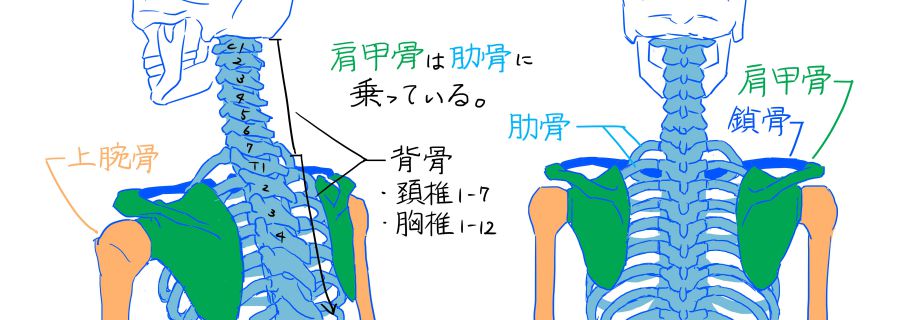
図1-2:後ろから見た肩の骨
肩甲骨は背中側にあり。
肋骨に乗っかっている。
また、肩甲骨は、
腕の骨である「上腕骨」に接続しています。
【図1-3:上から見た肩の骨】
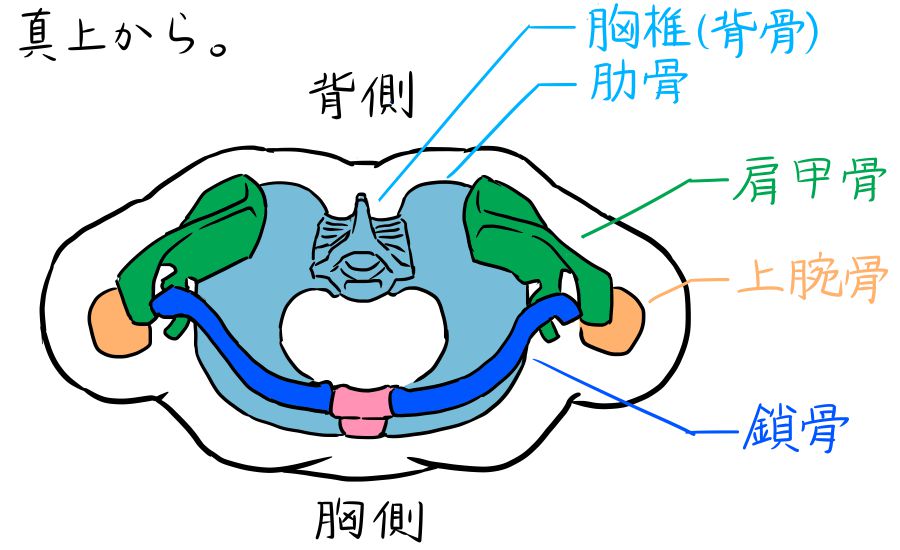
図1-3:上から見た肩の骨
真上から見てみると、
鎖骨と肩甲骨が、首をはさんで
ぐるりと囲んでいる形になっている。
【図1-4:上から見た肩の骨~おまけ】
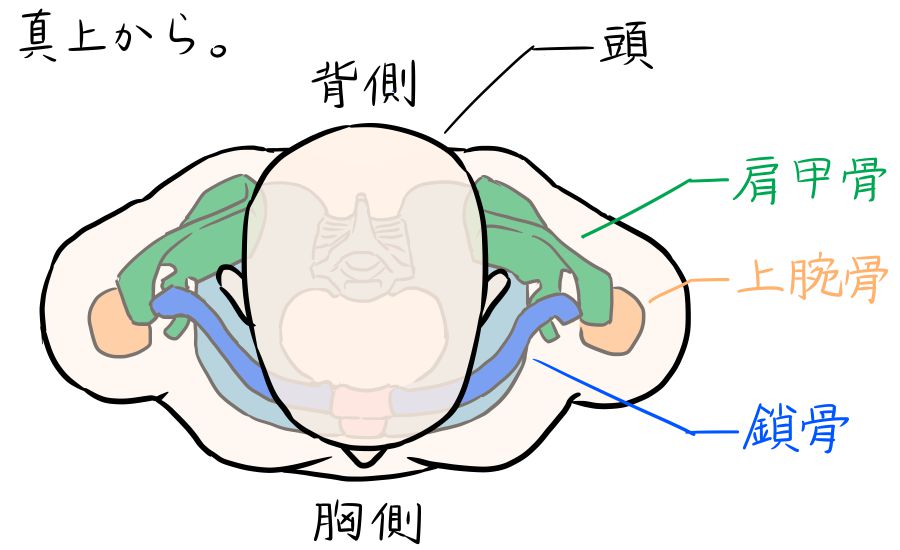
図1-4:上から見た肩の骨~おまけ
頭を乗せるとこんな感じ。
だいたいこんな感じだよ~という
雰囲気がわかればいいでしょう。
細かい部分にこだわる必要はないのです。
骨は筋肉に覆われ皮膚に覆われ…
まぁ、骨の外側は、筋やら筋肉やらが
何重にもあるわけなので、
詳細に理解する必要もないかなと。
なのでだいたいの位置と形を知っておく
だけでいいでしょう。
だいたいの形状を知っておくだけでも、
イラストを描くときにとても役立ちます。
形が大きく歪むことが避けられるし、
ポーズを付けるときにも変な形には
なりづらいかなと思います。
肩の構造を簡単なイラストにする
肩の骨がどんなふうになっているのか、
なんとなくわかったと思います。
では次に、イラストを描くためには
どうするのか?ですね。
キャラクターイラストを描く時には
まず下描きをします。
下描きの方法は人それぞれですが、
細かい骨の形などを気にしていると
疲れてしまいます。
そこで身体のパーツの位置を把握しつつ
下描きをすませるために、
「自分なりに簡単に図形化する」
ということをしてみましょう。
さて、先程の骨の図を単純化してみます。
【図2-1:肩の構造~単純化した図前】
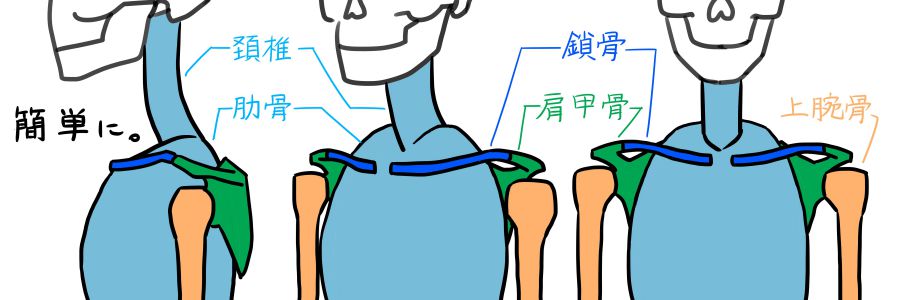
図2-1:肩の構造~単純化した図前
【図2-2:肩の構造~単純化した図後ろ】
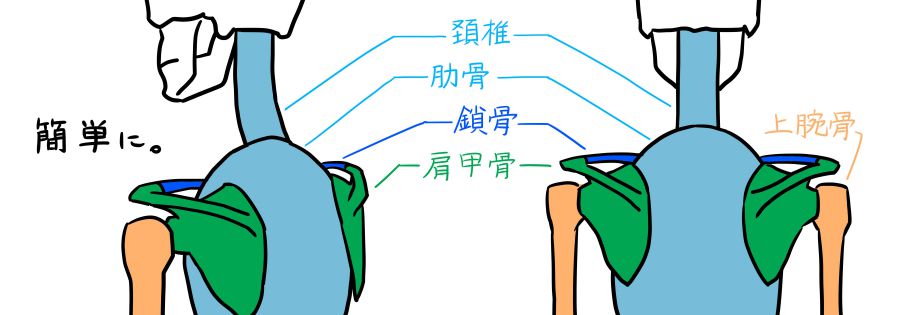
図2-2:肩の構造~単純化した図後ろ
首の骨(頚椎)も肋骨も、
ひとつの塊としてとらえる。
そこに鎖骨と肩甲骨が乗っかっている。
肩甲骨は特に複雑な形状をしていますが、
細かいことを気にせずに
単純な形として見てみましょう。
鎖骨(青色)と肩甲骨(縁色)の
位置と形を、だいたいでいいので
覚えましょう。
頭(頭蓋骨)とかも
簡単に形を描いておけばいいですよ。
絵を描くことって、
だいたいの形が取れるようになれば
上手く描けるようになっていきます。
身体の外から見える鎖骨と肩甲骨
普通に人物を描くときには、
骨ではなく、皮膚の外側の状態を捉えて
描きますよね。
外見でわかる肩周りの骨も、
鎖骨と肩甲骨。
その他は筋肉が浮き出て見えるのです。
外見から骨はどのように影響して見えるのか
図にしてみました。
【図3-1:身体の中の鎖骨と肩甲骨~前・横】
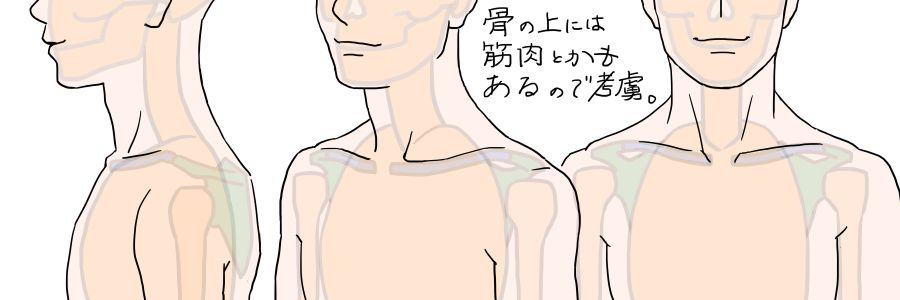
図3-1:身体の中の鎖骨と肩甲骨~前・横
【図3-2:身体の中の鎖骨と肩甲骨~後ろ】
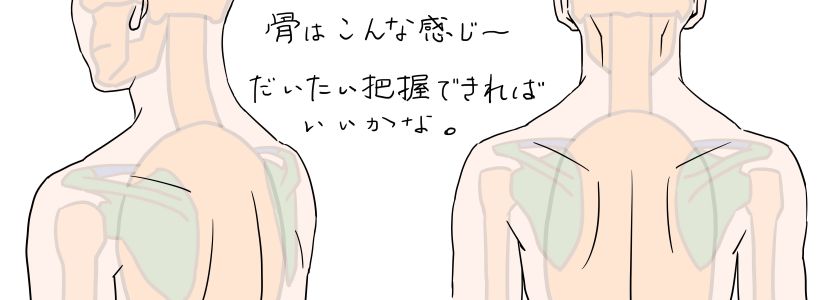
図3-2:身体の中の鎖骨と肩甲骨~後ろ
鎖骨と肩甲骨は外から見て取れる。
(皮膚表面に浮かび上がる)
骨や筋肉の位置、形などを知っておくと、
イラストを描く時に、身体のどのあたりに
線を入れるとそれらしく見えるのか、
ということがわかるようになります。
ま、ここでは筋肉を割愛していますけど…
そのうちやります^^;
鎖骨は自分でも鏡で見ることができるので
確認しやすい部分ですが、
肩甲骨はなかなかそうもいかないですよね。
映画やドラマ、写真などで見る機会があれば
じっくりと観察してみましょう。
…生身の人を見るときには
ガン見しないよう気を付けましょうね~^^;
(不審者認定されてしまいます)
肩回りは立体的に考えるのが難しい
と感じますが…。
胸骨からの鎖骨と肩甲骨、
そして上腕骨とのつながりが理解できると
イメージがしやすくなります。
今すぐにイメージできなくても当然なので、
焦らずじっくりと把握して行きましょう^^
まとめ
肩まわりを描くためには…
- 肩まわりの構造を知ること
- 自分なりに単純化、図形化してみること
- 構造を理解してイメージしてみること
肩の骨は「鎖骨」と「肩甲骨」
このつながりを知ると
肩回りを描くのがずっと楽になります。
基本的にイラストを描く上では
すべての骨や筋肉を知る必要はないのです。
描くために必要な部分というのは
人によって違うと思いますが、
「自分がどんなイラストを描きたいのか」
というところに関わります。
誰でも知っておくといい部分はというと、
大まかな骨格と肌の表面に近い部分の筋肉。
初めに骨から知っておくといいのは、
骨は身体の土台であるし、
骨の形がわかっていれば、
極端におかしな絵にはならない
というところですね。
そして、より理解が深まりやすいのです。
それでは今回もおつかれさまでした。
楽しいお絵かきライフを
お過ごしくださいな~^^